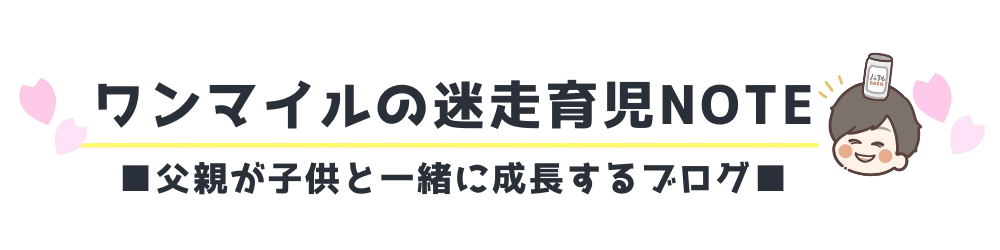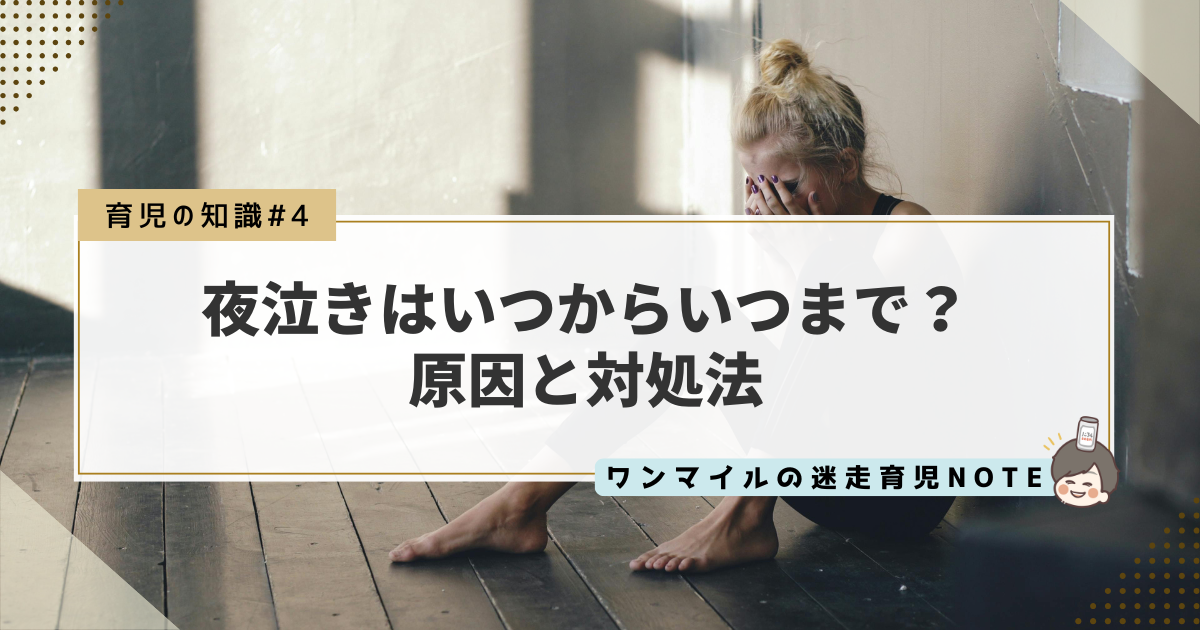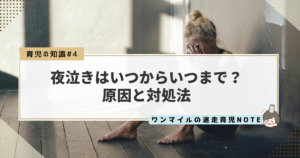子どもが寝ていると思ったら突然の泣き声…。
「もう寝てくれ〜」と夜中にため息をついた経験、子育てをしていると誰しも一度はあるのではないでしょうか。
この記事では、夜泣きの基本知識と原因、そして親ができる対処法について解説します。
 ワンマイル
ワンマイル子育て最初の関門「夜泣き」どうやって乗り切るか、一緒に考えていきましょう!
夜泣きとは?
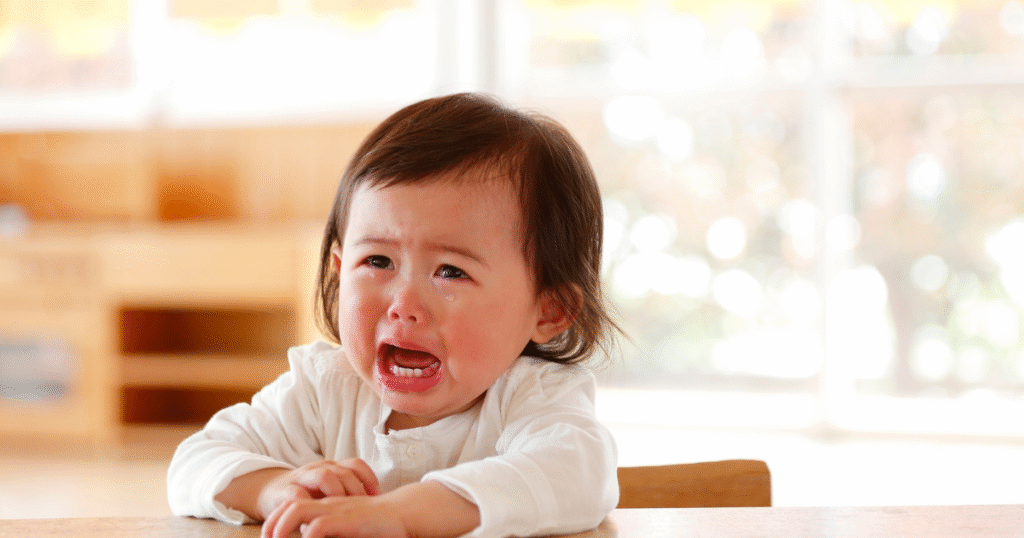
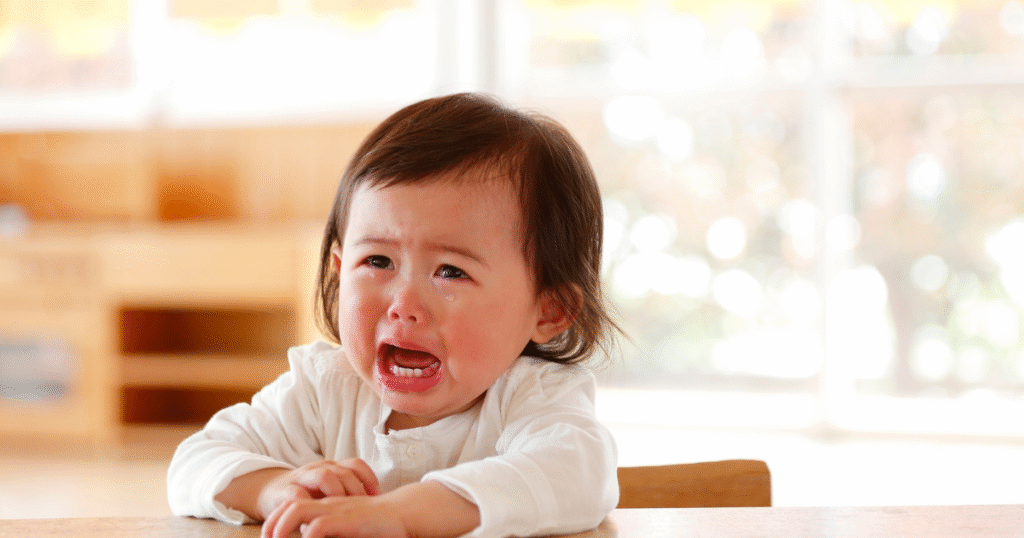
夜泣きとは、赤ちゃんや幼児が夜中に突然泣き出すことをいいます。
特に多いのは 生後6か月〜1歳半ごろ。ただし個人差があり、3歳ごろまで続く場合もあります。
重要なのは、夜泣きは病気ではなく「成長の過程」であるということ。脳や神経が急速に発達しているサインでもあります。とはいえこの期間は体力もメンタルもやられがちになります。



夜泣きに関してはセブンもキティもありました。セブンは長引きましたが、キティは烈火の如く泣き喚き強烈でした。
夜泣きの主な原因


夜泣きには明確な原因が一つあるわけではありません。いくつかの要因が組み合わさって起こることが多いです。
• 生活リズムの乱れ:昼寝が長すぎる/就寝時間が遅い
• 不安や寂しさ:親の姿が見えなくなると泣く、引っ越しなど環境の変化
• 体調や成長の影響:鼻づまり、歯の生え始め、成長痛など
• 脳の発達:眠りのサイクルがまだ安定しておらず、浅い眠りから目が覚めやすい



後でそうだったのかな?と思って申し訳なくなったのですが、セブンは何年もずっと鼻詰まりでした。毎晩苦しくて寝付けずにしんどかったと思います。
ごめんねセブン😭
親ができる対処法
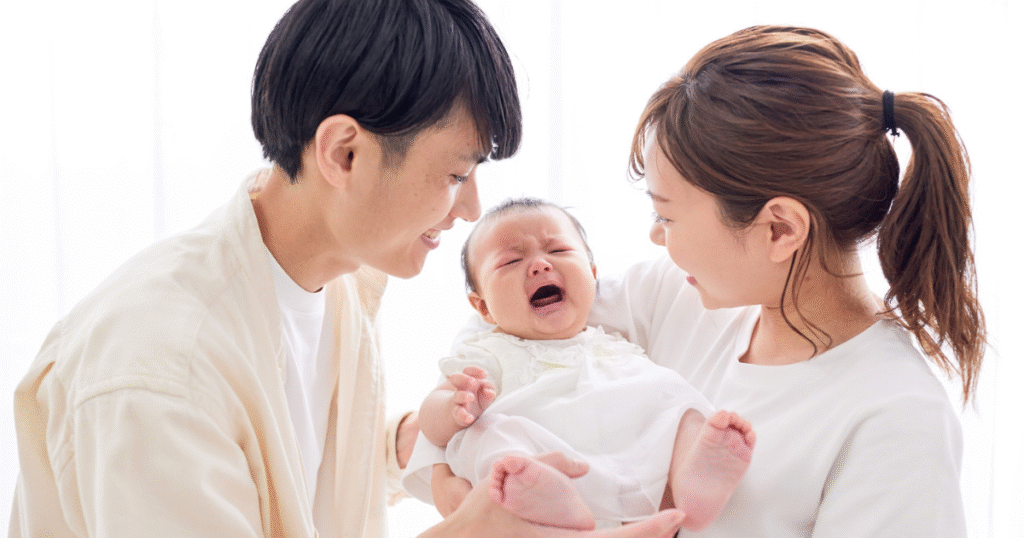
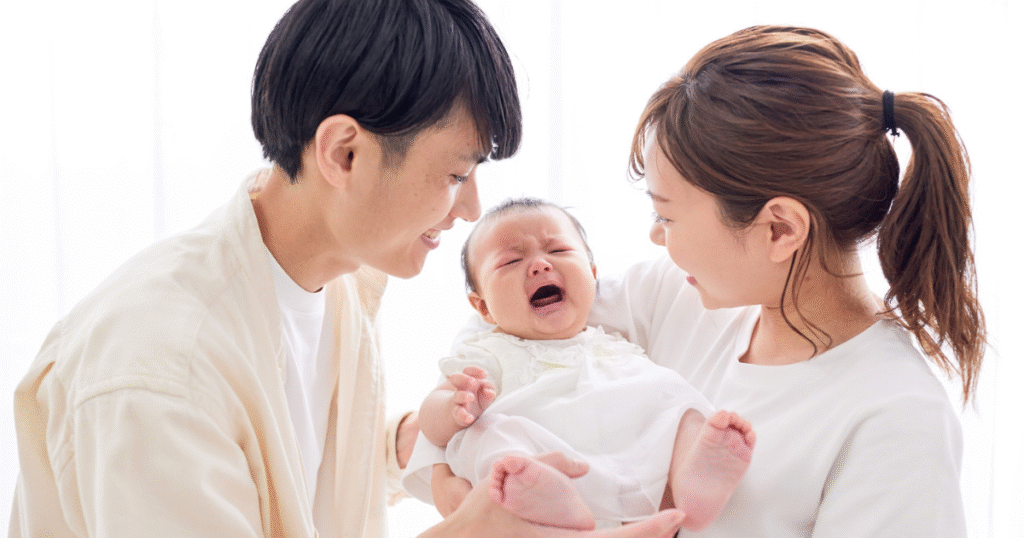
夜泣きを完全になくすことは難しいですが、工夫で和らげることはできます。
• 環境を整える
部屋を暗く、静かにして安心できる空間をつくる。室温や湿度も大切です。
• 入眠儀式を決める
寝る前に絵本を読む、音楽をかける、スキンシップをするなど「眠る合図」を習慣に。
• 泣いたらすぐ抱っこではなく工夫を
まずはトントンや優しい声かけで落ち着くか試してみる。それでも難しいときは抱っこで安心させましょう。
• 昼間の活動量を増やす
外遊びや運動で体を動かすことで、夜の眠りが深まりやすくなります。



2人の子と夜泣き期間を経て思うのは、昼間の活動量を増やすのは一理あると思います。どれだけ元気な子供でも疲れたらさすがに爆睡します。
避けたいNG対応
ついしてしまいがちな対応もありますが、逆効果になってしまうことがあります。
• イライラして強引に泣き止ませようとする
• スマホやテレビを夜中に見せて落ち着かせる
これらは一時的には静かになっても、習慣や安心感に悪影響を与えることがあります。
親のメンタルケアも大事
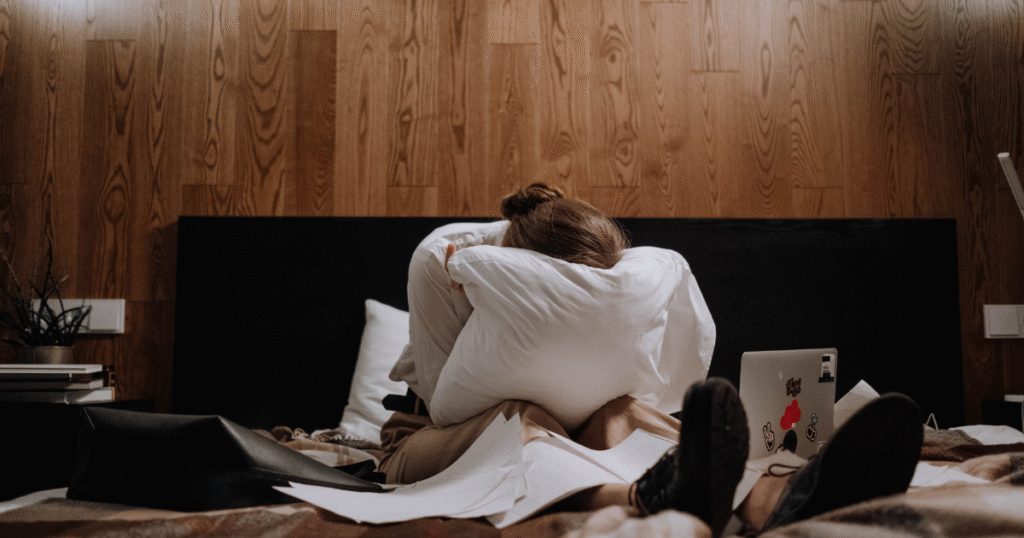
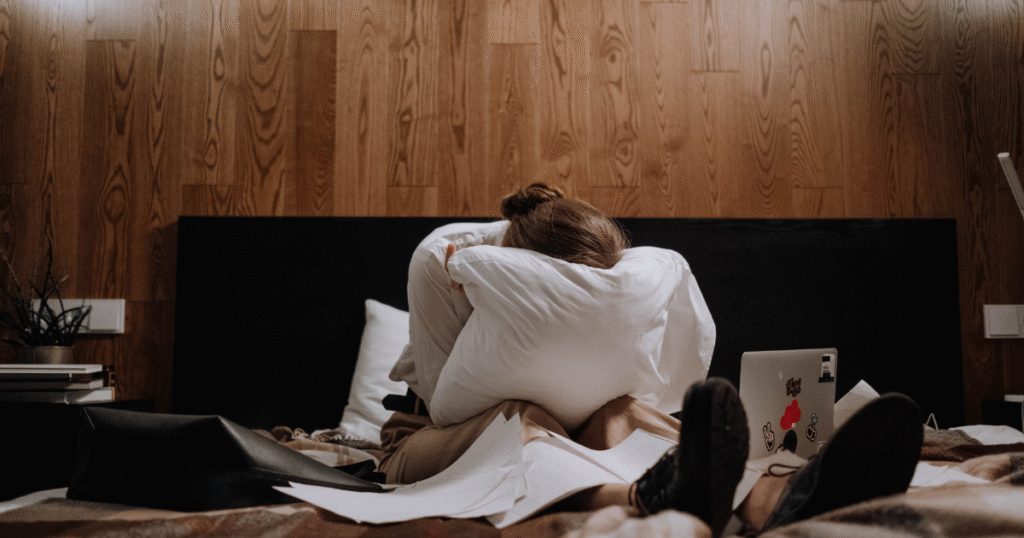
夜泣きが続くと、親のほうが疲れ果ててしまいます。
• 夫婦で交代して睡眠を分担する
• 実家やファミリーサポートを頼る
• 「今日は寝かしつけは諦めて一緒に寝てしまおう」と割り切る
完璧を目指さず、親の休息も優先しましょう。親が元気でいることが、子どもにとっても一番の安心になります。
まとめ:どうやり過ごすか


大体よく、「泣き声に疲れてしまう日もありますが、これも成長の証と捉えることで気持ちが少し楽になるはずです。
子どもと一緒に、親も少しずつ成長していければ大丈夫。焦らず、今この時期を乗り越えていきましょう。」
みたいなことが言われていますが、夜泣き期間は体力がやられメンタルもやられる地獄の消耗戦です。
この期間をいかにやり過ごすか、難しければほっぽりだせる事柄はないか。できるだけ自分を軽くできないか探してみるのも手です。



前回の言葉の遅れもそうなのですが、一定期間耐え忍ばないといけないことが
いくつかあります。その中のひとつです。この時期は休める時は無理にでも休め。精神で乗り切りましょう!最後までお読みいただきありがとうございました。