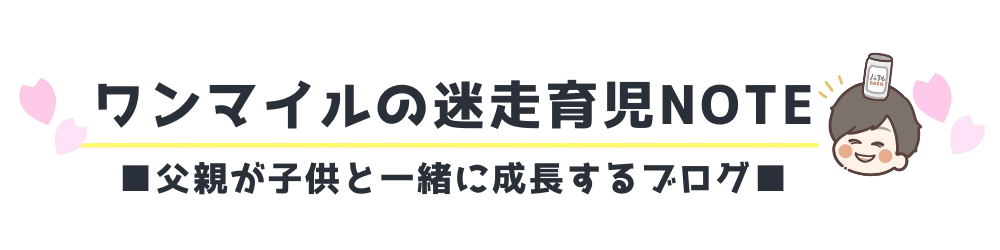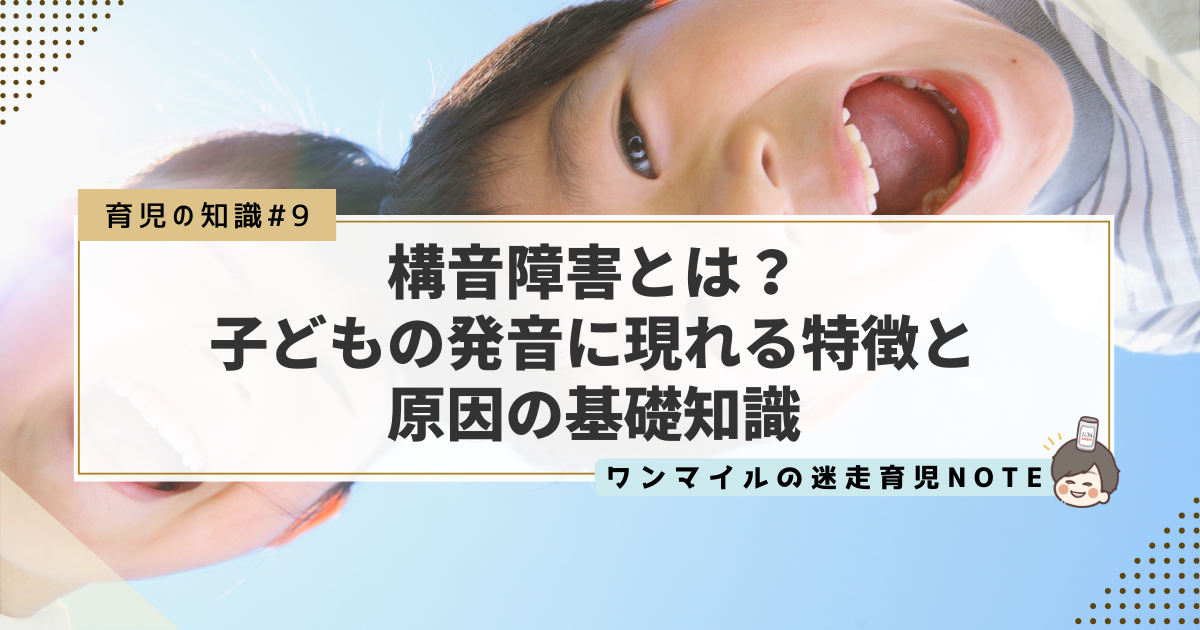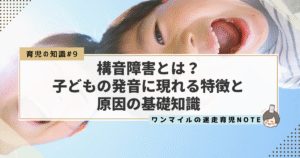「さかな」が「たかな」になったり、「くつ」が「ちゅ」になったり──。
幼児期の子どもの言葉を聞いていて、「あれ、うちの子ちょっと発音が気になるかも?」と思う瞬間、ありますよね。
小さな子どもはもともと発音が未熟で当然です。3〜4歳ごろまでは、多くの子が言葉の発音を練習している段階にあります。
しかし、年齢が上がっても特定の音がはっきり言えない、いつまで経っても「言い間違い」が直らない――そんな場合に考えられるのが「構音障害(こうおんしょうがい)」です。
 ワンマイル
ワンマイル今回は、構音障害とは何か、どんなタイプがあるのか、そして原因としてどのようなことが考えられるのか等、親が最低限知っておきたい基礎知識を書いてみました。
構音障害とは?
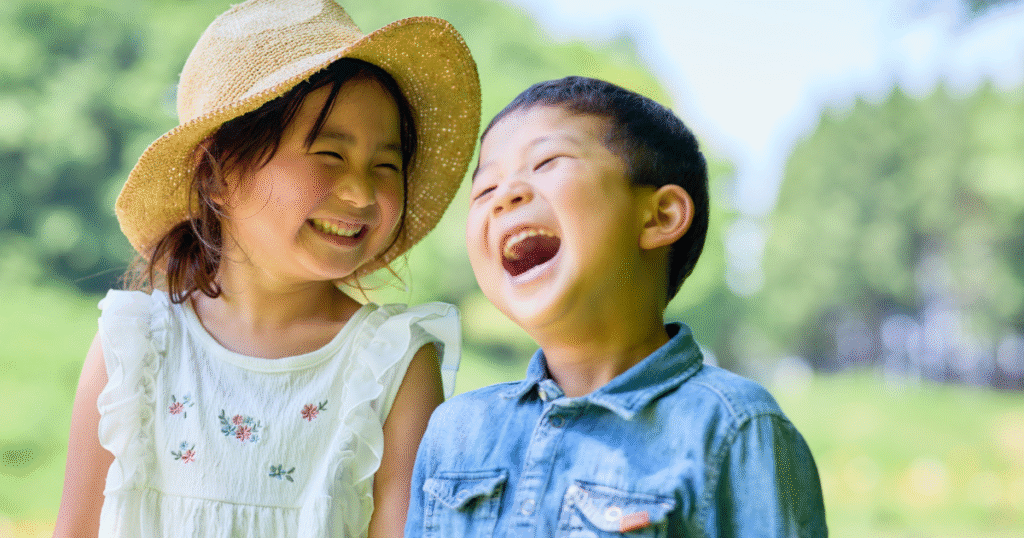
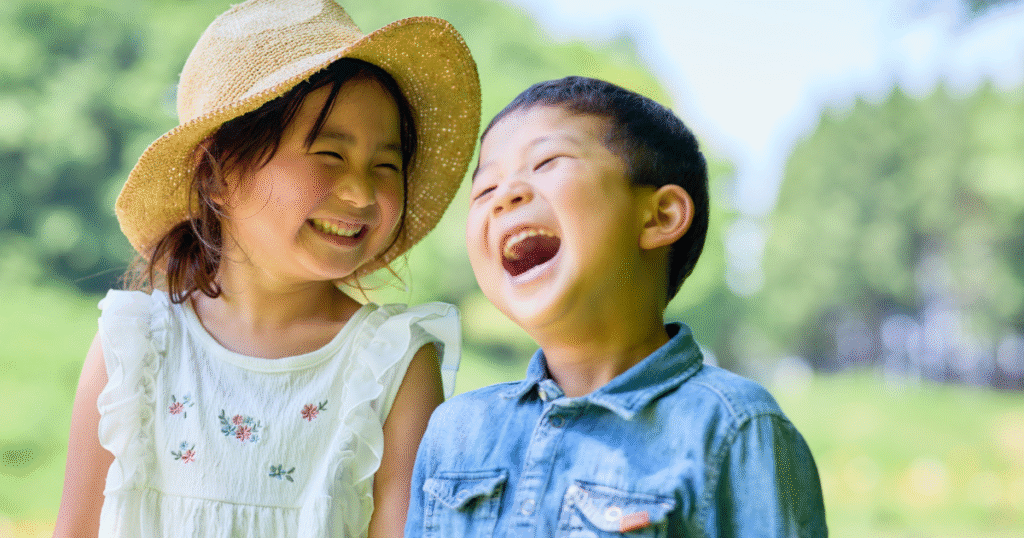
構音障害とは、正しい音を出すための「口の動き」や「息の使い方」が上手くいかず、言葉の発音が不明瞭になる状態を指します。
人は言葉を話すとき、舌・唇・あご・声帯・鼻腔など、多くの器官を連動させて音を作っています。
構音障害があると、これらの動きのどこかにズレや制限が生じ、音を正確に作り出せなくなります。
構音障害は、知的な遅れや発達障害がなくても起こることがあるため、知能や性格とは切り離して考える必要があります。



発音に関してはいつか言えるようになるとは思っていても、時が経つにつれだんだん不安になってきます。
構音障害の種類
構音障害には、主に次の3つのタイプがあります。
① 機能的構音障害
器官の形や神経に問題がないのに、正しい発音の習得がうまくいかないタイプです。
たとえば、「サ行」や「ラ行」など発音が難しい音を誤って覚えてしまい、そのまま癖になっているケースです。
多くの構音障害はこの「機能的構音障害」に分類され、言語聴覚士による訓練で改善が見込めます。
② 器質的構音障害
発音に関わる器官(舌・口蓋・唇など)の形や動きに、先天的・後天的な異常がある場合です。
例として、口唇口蓋裂、舌小帯短縮症(舌の裏のひもが短い)、歯列不正、慢性的な鼻づまりなどが挙げられます。
器質的な原因がある場合は、発音指導と並行して、耳鼻科や歯科、形成外科での治療が必要になることもあります。
③ 運動障害性構音障害
脳や神経の働きが発音運動に影響しているタイプです。
脳性まひや小脳疾患など、神経系の障害によって口や舌の動きが不安定になるケースが該当します。
この場合も医療的サポートが中心となります。
構音障害によくみられる特徴
構音障害がある子どもの発音は、一見「かわいい言い間違い」に聞こえることもあります。
しかし、年齢が上がっても以下のような傾向が続く場合は注意が必要です。
• 「サ行」が「タ行」「シャ行」に置き換わる(例:「さかな」→「たかな」「しゃかな」)
• 「ラ行」が「ダ行」「ナ行」になる(例:「りんご」→「にんご」「でんご」)
• 「カ行」「タ行」「ハ行」など、特定の行の発音が不明瞭
• 長い言葉になると音が崩れやすい
• 友達や先生に「え?」と聞き返されることが多い
これらは、構音運動がうまく連携していないサインの一つです。



セブンの場合は、カ行とサ行が全部タ行になっていたのが印象的でした。
つみき→つみち
せんたく→てんたつ
しんかんせん→ちんたんてん
構音障害と鼻詰まりの関係
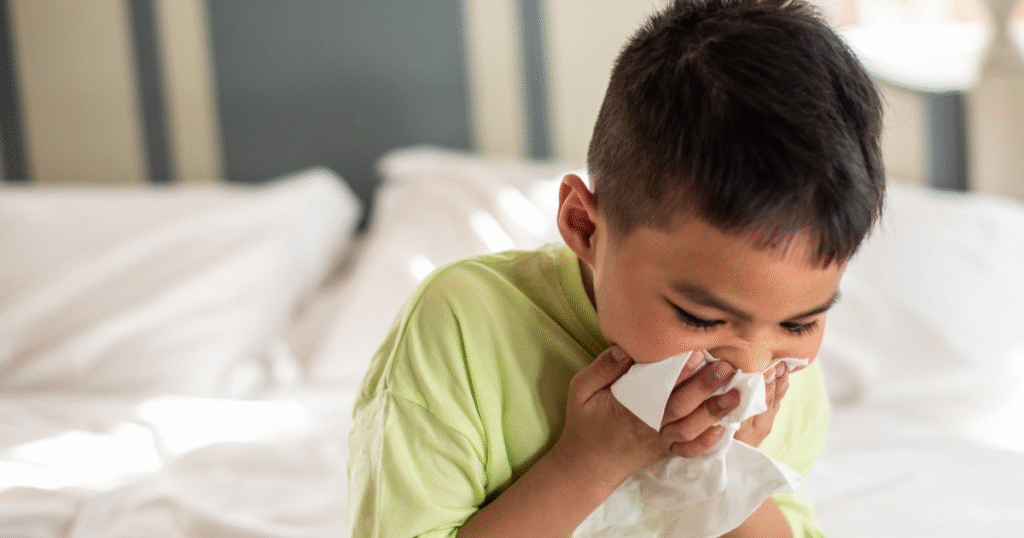
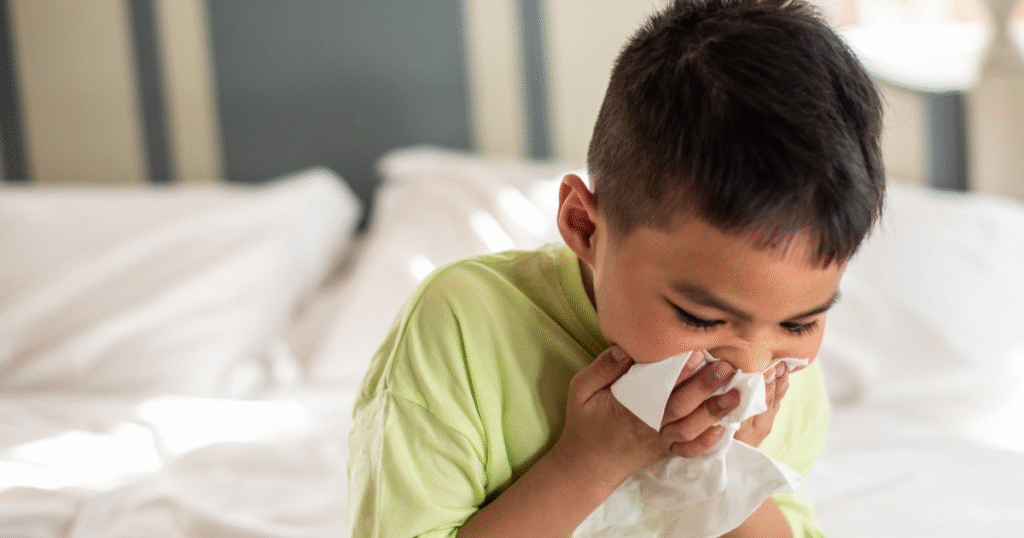
意外に見落とされがちなのが、「鼻詰まり」と発音の関係です。
構音において、鼻は「共鳴(きょうめい)」と呼ばれる重要な役割を担っています。
通常、鼻から抜ける息の量を調整しながら「ま行」「な行」などの音を作っています。
しかし、鼻づまりが続くと、この空気の通り道が塞がれてしまい、音がこもる・息が抜けない・声が鼻声っぽくなるといった状態になります。
この状態が長引くと、子どもが鼻呼吸ではなく口呼吸に慣れてしまい、舌や唇の使い方も不自然になります。
結果として、「息を出す方向」「舌の位置」「口の開き方」が崩れ、構音の基礎動作が乱れてしまうのです。
耳鼻科の診察では、アデノイド肥大やアレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎などが背景にある場合もあります。
発音が気になるときは、まずこうした身体的要因を除外することが重要です。



セブンはずっと鼻づまりだったんです。
発音と鼻づまりの関係については、最近そうかも?と思うようになったんです。もっと早く気づいていれば、鼻づまりの改善を模索していれば、セブンに苦しい思いをさせなくて済んだかもしれません。
いまでも後悔しています。
構音障害の発生時期と発達との関係
子どもが日本語の音をマスターするのは、おおよそ6歳前後といわれています。
そのため、3〜4歳ごろに多少の言い間違いがあっても、焦る必要はありません。
ただし、5歳を過ぎても特定の音が安定しない場合、言語聴覚士による評価を受けておくと安心です。
幼児期に誤った発音が定着すると、学校生活や対人関係で「聞き返されやすい」「自信をなくす」といった二次的な影響につながることもあります。
構音障害と「言葉の遅れ」「レイトトーカー」との違い


構音障害は「音を作る動きの問題」であり、
一方の「言葉の遅れ(レイトトーカー)」は「語彙や文法など言語の理解・表現の問題」です。
つまり、
• 構音障害 → 言いたいことは理解しているが、うまく発音できない
• 言葉の遅れ → 言いたい言葉そのものの表現の仕方がわからない
という違いがあります。
ただし両者が併発することもあり、発音が不明瞭なために「言葉が少なく見える」ケースもあるため、専門的な評価が欠かせません。
診断と対応の流れ


構音障害が疑われる場合、まずは耳鼻咽喉科や小児科で身体的要因を確認します。
その上で、必要に応じて言語聴覚士(ST:Speech Therapist)による構音検査や言語評価を受ける流れになります。
言語聴覚士による訓練は、正しい舌の位置・息の出し方・口の形などを一つずつ練習し、
誤った癖を少しずつ修正していく形で進められます。



セブンはすぐれた言語聴覚士さんとの出会いにより10ヶ月程で
すべての発音が改善しました。言語聴覚士の訓練を受けることは必須だと思っています。少しでも気になることがあれば、支援機関を通じて相談しましょう。
まとめ
構音障害は、見た目では気づきにくいものの、発音の基礎である「口・舌・鼻・息」の動きがうまく噛み合っていない状態です。
特に鼻づまりや舌の可動域の問題など、身体的な要因が関係していることも少なくありません。
3〜4歳の段階では「成長の途中」であることも多いですが、5歳を過ぎても音が安定しない場合は、専門機関で一度チェックしておくのが安心です。
子どもの「話したい」「伝えたい」という気持ちを支えるためにも、発音に関する小さな違和感を見逃さず、正しい知識を持って見守ることが大切です。



子どもに合った言語聴覚士と出会うことで、セブンのように劇的に改善する可能性があります。言語聴覚士さんとの出会いは記事にしたいと思います。
最後までお読みくださりありがとうございました。