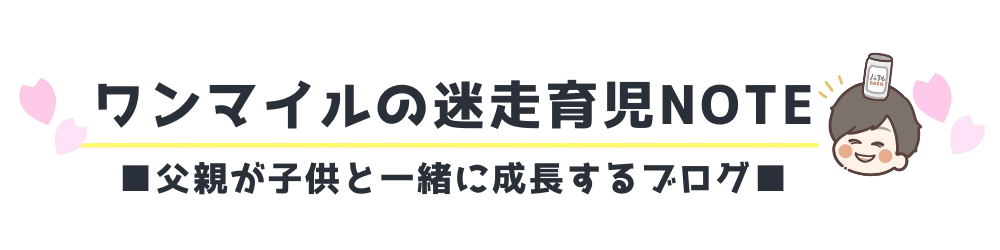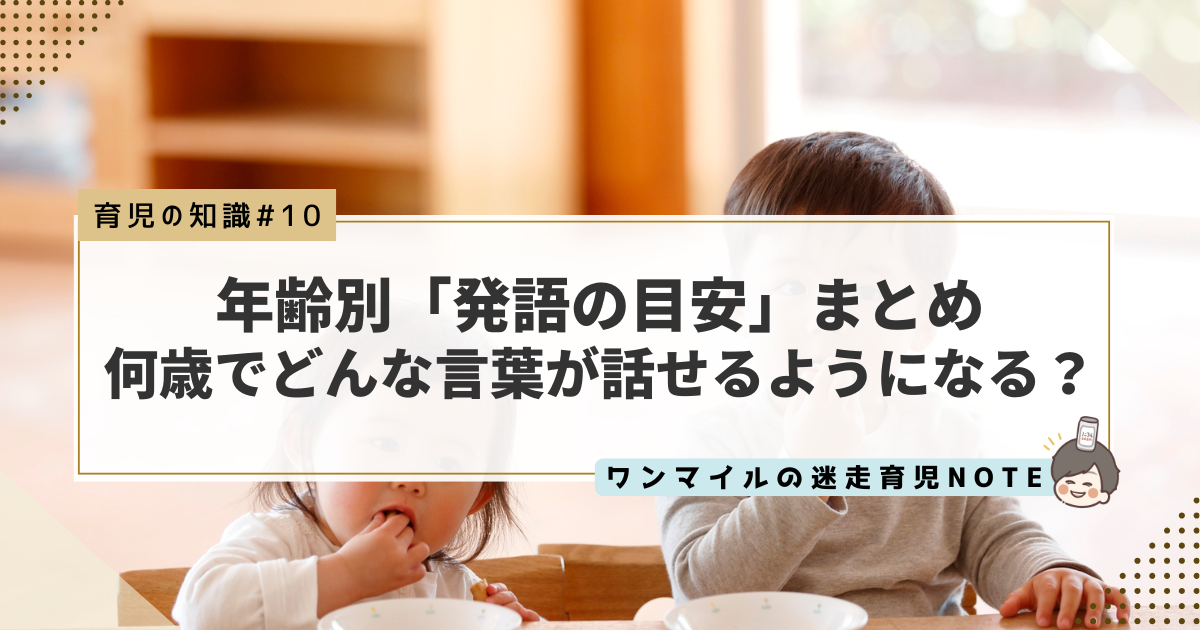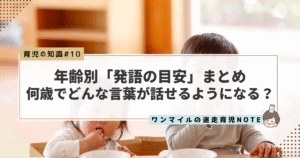「うちの子、まだ全然しゃべらないけど大丈夫かな…」
子育てをしていると、一度はそんな不安を抱くと思います。
周りの子が流暢におしゃべりしているのを見ると、つい比べてしまう。
けれど、言葉の発達には思っている以上に「個人差」があります。
この記事では、発語の基本的な流れと年齢別の目安。
そして発語の遅れが気になる場合に考えられる要因を基礎知識としてわかりやすくまとめます。
焦らず、そして正しい理解を持って子どもの言葉の成長を見守るための参考にしてください。
発語とは?

発語(はつご)とは、単に“声を出す”ことではなく、意味のある言葉として音を使うことを指します。
たとえば「アー」「ウー」といった喃語(なんご)は発声であり、まだ発語ではありません。
発語ができるようになるには、
音を聞き取る力(聴覚)
音をまねる力(運動機能)
言葉の意味を理解する力(認知)
の3つがそろう必要があります。
つまり「話す」という行為は、単なる口や舌の動きではなく、脳・耳・口の協調動作なんですね。
そのため、発語の発達には時間がかかるのが自然です。
年齢別・発語の目安

では、一般的にどのくらいの年齢でどんな言葉を話すようになるのでしょうか。
もちろん個人差はありますが、おおよその発達の流れを知っておくと安心です。
1歳前後
この時期は、まだ「喃語(なんご)」の段階です。
「バババ」「マママ」など、特定の意味を持たない音を繰り返します。
しかし1歳を過ぎると、「ママ」「ワンワン」など、意味を理解したうえで言う単語が少しずつ出てくるようになります。
1歳半〜2歳頃
単語が増え、「ママきた」「ワンワンいた」など、2語文を話すようになります。
このころは語彙が急速に増える時期で、「言葉の爆発期」とも呼ばれます。
身近な人や物の名前、動作などをどんどん覚えていく姿が見られるでしょう。
2歳〜3歳頃
「パパおしごといった」「これたべたい」など、簡単な文章を使って会話をするようになります。
発音はまだ不明瞭な部分もありますが、意思疎通はある程度可能になります。
3歳〜4歳頃
文法の基本が整い始め、発音も明瞭になっていく時期です。
質問に答えたり、簡単なストーリーを話したりと、会話のやりとりがスムーズになります。
このころになると、他人にも何を話しているのかが伝わるようになります。
5歳〜6歳頃
この頃には発音の多くが完成し、複雑な会話もこなせるようになります。
語彙力も豊かになり、感情や考えを言葉で表現できるようになるでしょう。
学校生活が始まる頃には、文法や語彙の基礎がほぼ整っていることが多いです。
 ワンマイル
ワンマイルセブンは2歳で喃語(なんご)を発するレベルでしたが、最終的には5歳〜6歳の時に発音は追いつきました。
発語の個人差について


発語の発達スピードは、本当に人それぞれです。
同じ年齢でも、3歳でスラスラ話す子もいれば、4歳を過ぎてから急に話し始める子もいます。
「平均」はあくまで統計的な目安に過ぎません。
歩き始める時期に個人差があるのと同じように、話し始めるタイミングにも幅があります。
ただし、もし以下のような様子がある場合は、一度専門機関に相談してみるのもよいでしょう。



セブンは素晴らしい言語聴覚士さんと出会ったことで、5歳時にいっきに伸びました。
発語の遅れが気になるとき


発語の遅れには、単なる個人差だけでなく、いくつかの発達的・身体的な要因が関係していることもあります。
代表的なものをいくつか挙げてみましょう。
構音障害(こうおんしょうがい)
構音障害とは、舌や唇、顎などの動きに問題があり、正しく音を発することが難しい状態です。
たとえば「さ行」「ら行」など、特定の音が言いづらい・置き換わる・抜けるといった特徴があります。
原因はさまざまで、鼻詰まりや扁桃肥大などによる口腔内の空気の流れの悪さが関係する場合もあります。
また、聴覚の異常や運動機能の発達の遅れが影響しているケースもあります。
構音障害が疑われる場合は、言語聴覚士(ST)による構音評価を受けることで原因が明確になり、専門的な訓練が行われます。
難聴
聞こえが悪いと、正しい音を覚えることが難しくなります。
そのため、発音や語彙の獲得が遅れることがあります。
耳鼻科での聴力検査は、言葉の遅れがある場合の重要なチェックポイントです。
発達性言語障害
発達の過程で、言葉の理解や表現に関わる脳の働きに偏りがあるケースです。
知的発達には問題がなくても、言葉だけが遅れることがあります。
専門の言語療法や療育支援が有効な場合もあります。
まとめ


言葉の発達には大きな個人差があり、焦りすぎる必要はありません。
しかし、「待てばそのうち話すだろう」と放置するのも避けたいところです。
もし2歳を過ぎても意味のある単語がほとんど出ない、3歳を過ぎても会話が成立しないなど、年齢に見合った発語が見られない場合は、早めに小児科や言語聴覚士に相談してみましょう。
専門家の判断を受けることで、現状を把握し、必要な支援を早期に始められます。
発語のスピードよりも大切なのは、まず現状を把握しできることを始めることです。
焦らず、温かく見守る姿勢が、ことばの芽を育てる第一歩になります。



言葉がかなり遅れていたセブンも、小学校入学前には皆に追いついた事実が
あるので、不安で仕方のない人は、やれることを探して早く動いた方がよいと思います。最後までお読みくださりありがとうございました。