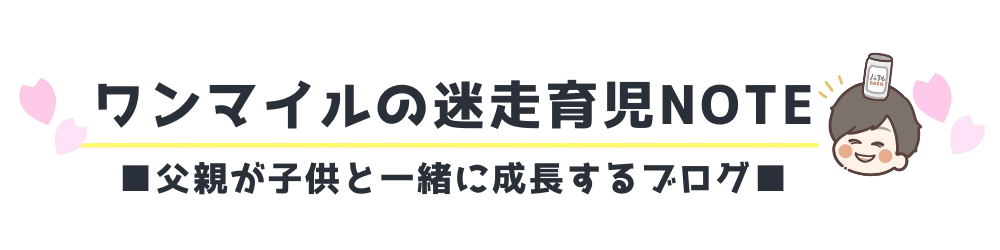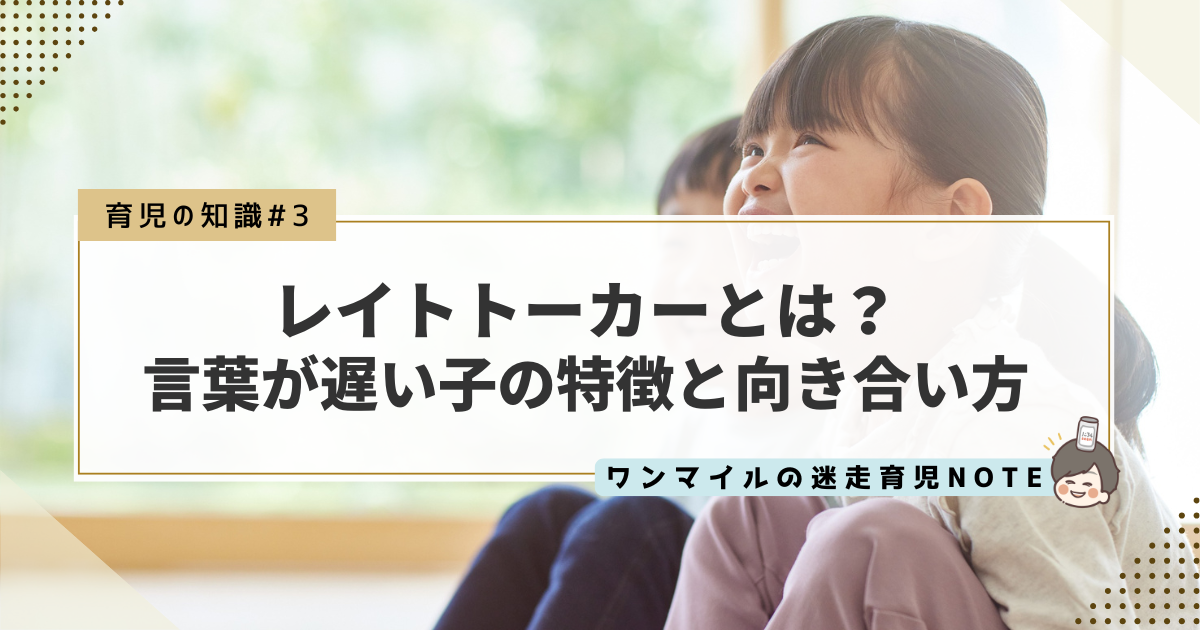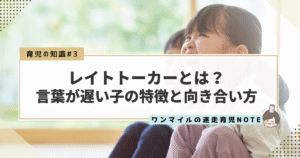レイトトーカーってなに?定義と診断の目安
子どもの発達には個人差が大きく、「言葉が遅い子」を指して「レイトトーカー(Late Talker)」と呼ぶことがあります。
一般的には、2歳を過ぎても使える単語が少ない/2語文にならないなどの状態を指すことが多いです。
ただし、これは医学的な診断名ではなく、あくまで発達の過程を表す言葉です。
健診や専門医が診断に使うものではない点は押さえておきましょう。
 ワンマイル
ワンマイルレイトトーカーという言葉は今回初めて知りました。
言葉が遅れる原因は1つじゃない
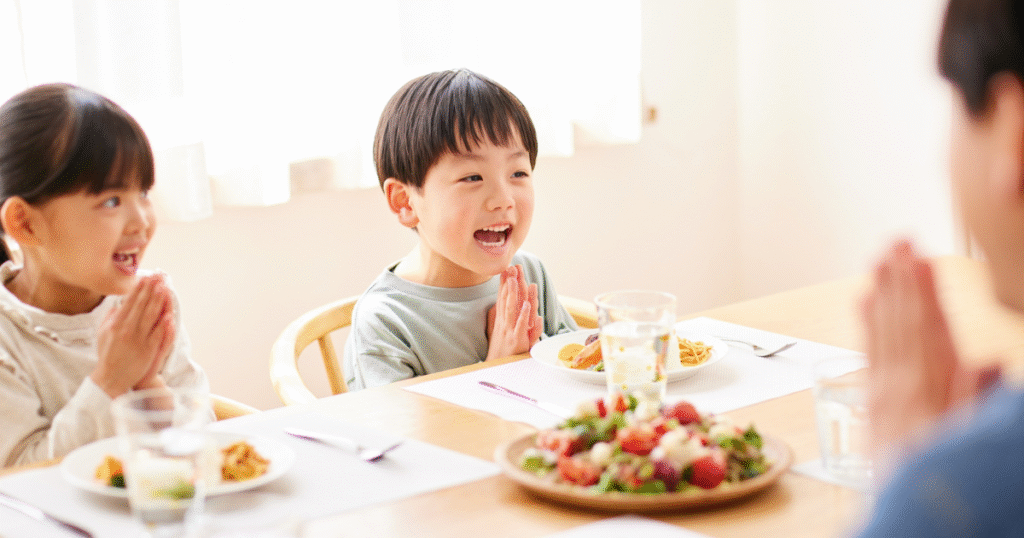
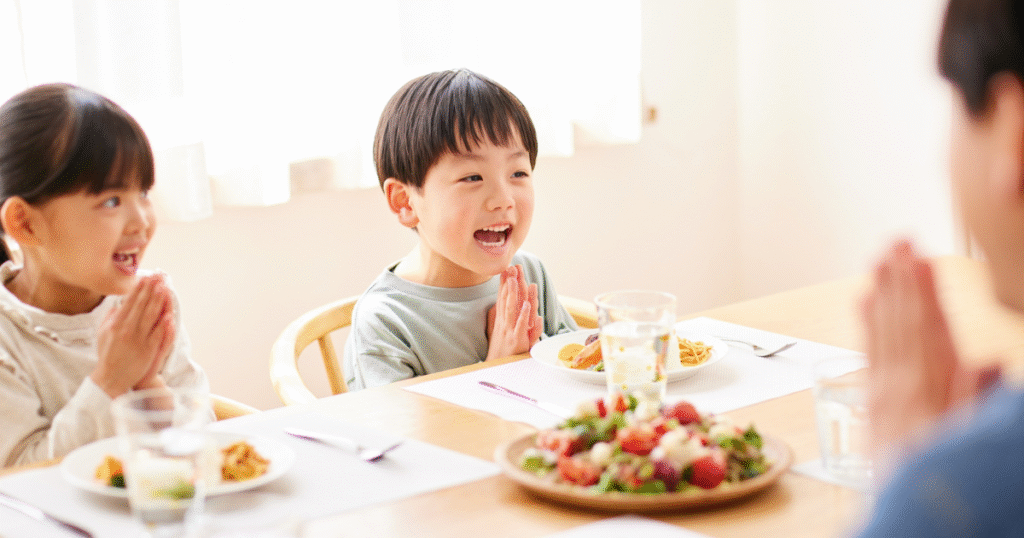
レイトトーカーには様々な背景があります。必ずしも「親の関わり方が悪い」わけではありません。
環境要因:家庭での会話量、テレビやタブレットの時間など
発達特性:ASD(自閉スペクトラム症)、聴覚障害、知的発達の遅れなど
性格・個性:おとなしいタイプや慎重な子は言葉が遅めになりやすい
要因が複合的に絡んでいるケースも多いため、単純に「これが原因」とは言えません。



2歳からは個人差なのか発達特性なのか、専門家に見てもらっても様子を見ましょう。となるので、もやもやしてしんどいですよね。
どんな特徴がある?家庭で気づきやすいサイン


以下のような特徴があるかと思います。家庭でも気づきやすいサインです。
✅言葉を発する気配がない、成長がほとんどみられない
✅言葉は少なくても、指差しやジェスチャーで気持ちを伝えようと
✅名前を呼ぶと反応するか、音に対して反応するか



セブンとは意思疎通がなかなかできず、言葉も出てくる気配がなかったのですが、こちらの言っていることをよく理解しているのはわかったんです。
受診や相談はどのタイミングで?


子どもの言葉の遅れが気になるときは、以下を目安にしましょう。
✅1歳半健診:意味のある単語が出ているか
✅3歳健診:2語文が出ているか、会話のやりとりができるか
気になる場合は、市区町村の保健センターや発達支援センター、かかりつけ小児科に相談できますが、
残念ながらはっきり遅れが確認できる年齢(4歳くらい)にならないと、個人差遅れの可能性がある為
様子見になります。



セブンの場合は3歳検診時であー、うーしか言えませんでしたが、発達支援センターへの相談を勧められることはなかったです。
家庭でできる関わり方


言葉の発達を促すために、家庭でできることもあります。
語りかけのコツ:「今ご飯食べてるね」「赤い車が走ってるよ」と、実況中継のように話す
読み聞かせや歌あそび:絵本や歌を通じて自然に言葉に触れる
NG対応:せかす、他の子と比べる、強制的に言わせようとする
「語りかけ」を大切にし、頻度を増やしいろいろな角度からじっくり行うことがポイントです。



当時はしつこく言葉を引き出そうとしてしまったことがありました。
はっきりとした原因はもう少し大きくならないとわからない以上、できるだけ割り切ってその日々を楽しく過ごせるように工夫してみましょう。
まとめ:焦らず、小さな成長を見逃さない


レイトトーカーは、成長のペースの一部であり、病気や障害とイコールではありません。
言葉は発達のひとつの側面に過ぎず、焦らず小さな成長を積み重ねることが大切です。



最後までお読みいただきありがとうございました。