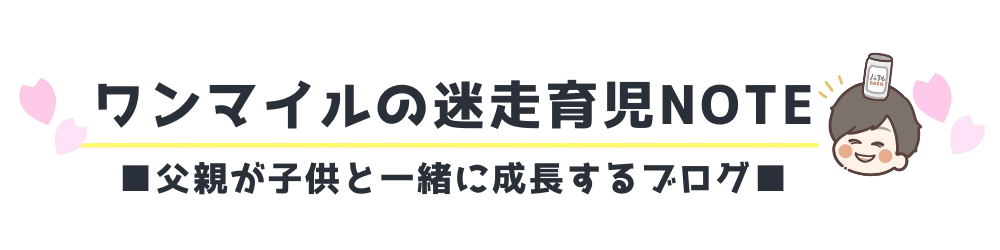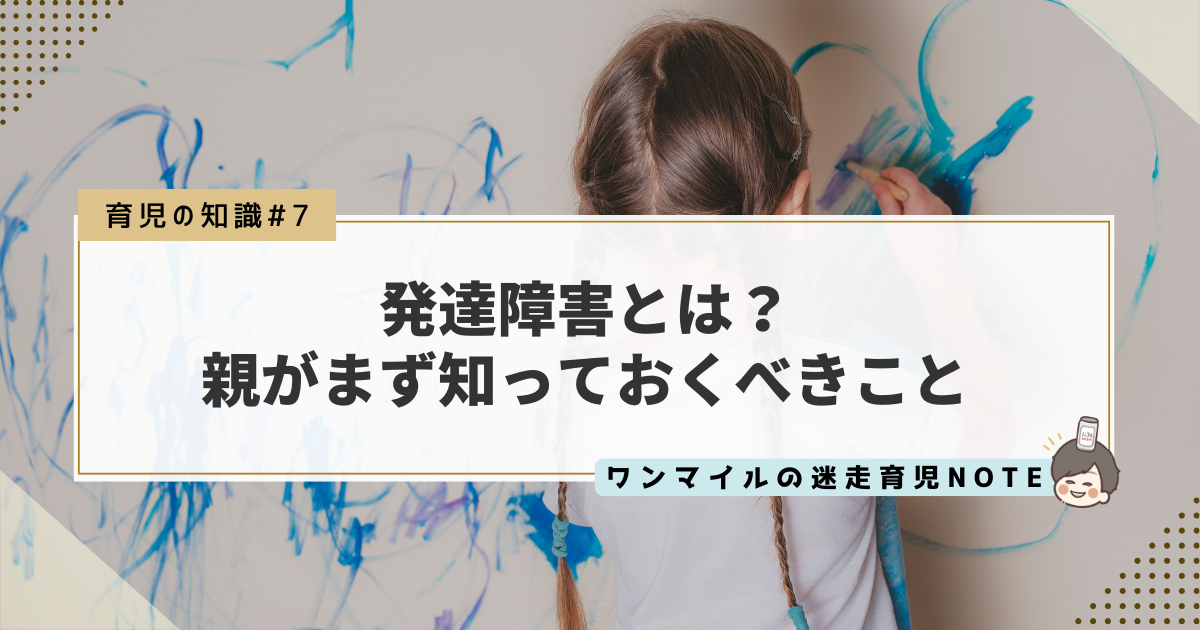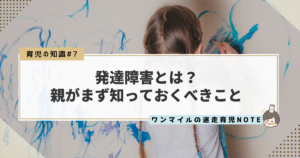こんにちは、ワンマイルです。
今回は「発達障害」について。
SNSやニュースでもよく耳にする言葉ですが、いざ我が子に関係あるかもしれない…となると不安でいっぱいになりますよね。
僕自身も調べれば調べるほど「情報が多すぎて何が正しいのかわからない」と迷いました。
この記事では、親がまず知っておく必要がある基本情報を、とことん調べて整理してみました。
発達障害とは?基本の理解

発達障害とは、生まれつきの「脳の発達の偏り」によって、生活や人との関わりに特徴が出る状態のこと。
代表的なのはこの3つです。
• 自閉スペクトラム症(ASD)
→ 人との関わりや感覚の特徴、こだわりの強さなど。
• 注意欠如・多動症(ADHD)
→ 集中しにくい、じっとしていられない、衝動的に動く。
• 学習障害(SLD)
→ 読む・書く・計算など、特定の分野だけ極端に苦手。
同じ診断でも子どもによって表れ方はまったく違います。
「障害」という言葉より「特性」として理解するとイメージしやすいかもしれません。
 ワンマイル
ワンマイル僕の小さい頃はこんな言葉1つもありませんでした。
年齢ごとに見られるサイン


「発達障害かも?」と思うサインは年齢によって異なります。
• 乳幼児期(〜3歳)
・目が合いにくい
・指差しや発語が遅い
・強いこだわり(同じ順番・同じ道でないとダメ)
• 幼児期(3〜6歳)
・集団での遊びが苦手
・落ち着きがない/じっとできない
・友達とトラブルになりやすい
• 学童期(小学校〜)
・忘れ物やミスが極端に多い
・授業中に集中できない
・読み書き・計算だけが苦手
ただし「発達のスピードには個人差がある」ことも大前提。
1つのサインだけで判断する必要はありません。



セブンに当てはまっていた項目に線を入れています。落ち着きがないじっとできないのは制御不能までではなかったです。
相談・診断の流れ


もし気になったら、どこに相談すればいいのでしょうか?
• 市町村の保健センター
発達相談や発達検査につないでくれる窓口です。
• 発達支援センター
専門スタッフが在籍しており、診断前から相談可能。
• 小児科・小児精神科
かかりつけ医から紹介を受ける流れも一般的です。
診断には発達検査(K式、WISCなど)、言語検査、行動観察などが行われます。
「診断の有無」で支援が変わる場合もあるため、迷ったら相談だけでもOKです。



相談するのは怖いけど、ずっとモヤモヤするので勇気を出して行ってみるのも一つです。セブンは言葉の意味は理解していたので、言語の支援だけ相談しにいきました。
支援や対応方法


発達障害に関する支援や環境が整ってきています。
• 療育(未就学児向け支援):遊びや日常生活を通してスキルを育てる。
• リハビリ(言語・作業療法など):言葉や手先の動き、感覚への対処を訓練。
• 学校での配慮:個別支援計画、座席の工夫、試験方法の調整など。
• 薬物療法(主にADHD):集中力や衝動性の改善をサポート。
• 親へのサポート:保護者学習会や支援グループで相談・情報共有。



もし違ったとしても早期に動いてみることは大切だと思います。
家でできる工夫
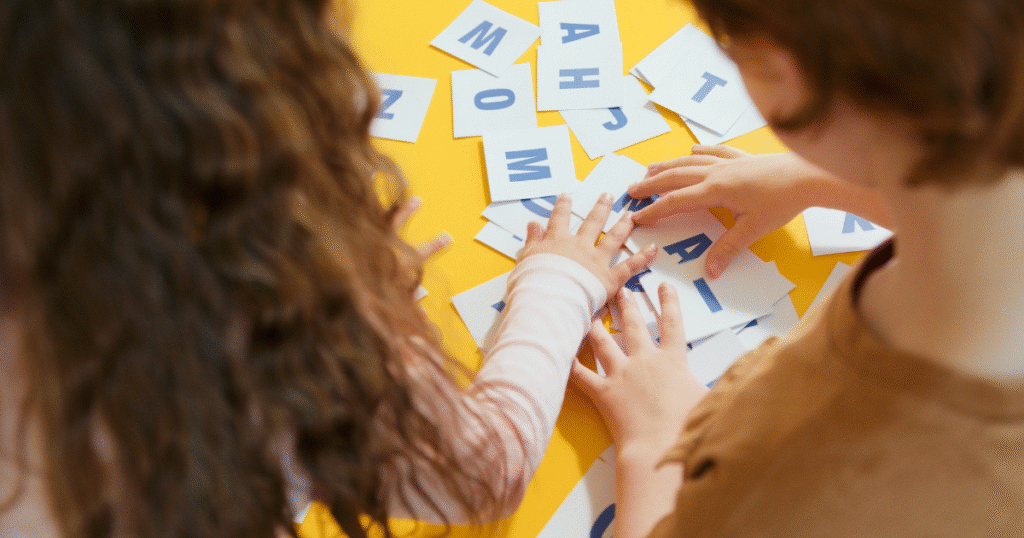
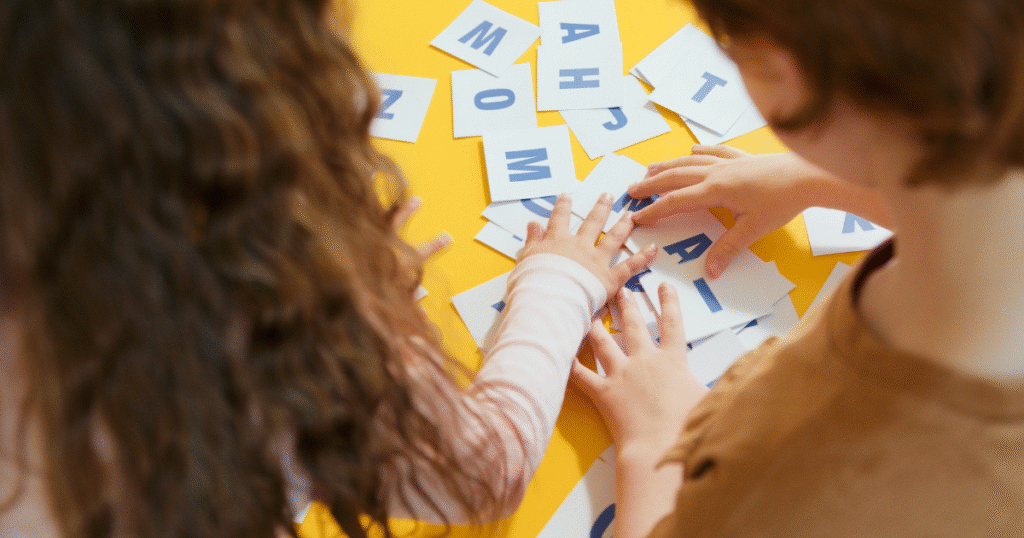
支援につながる前からできる工夫もたくさんあります。
• 生活のルーティン化:毎日同じ順番で行動する安心感。
• 視覚的サポート:言葉だけでなく、絵やカードで伝える。
• 短い指示:「ご飯のあとで着替えよう」のように一つずつ。
• 成功体験を積ませる:できたことをその場で褒める。
• 感覚に合わせる:音に敏感ならイヤーマフ、着心地に配慮する服など。
• 親自身が休む時間をつくる:孤独感が一番の敵です。
「完璧な対応」より「少しラクにできる工夫」を積み重ねることが大切です。



生活の中で色々やってみて、どうしても難しい部分が出てくればピンポイントで相談すると効果的です。その特性に特化した支援施設も紹介してくれます。
園や学校とのつきあい方


園や学校に特性を伝えるのは勇気がいりますよね。
でも先生に理解してもらえると、子どもも親も本当にラクになります。
• 具体的に「困る場面」「うまくいく場面」を伝える
• 家で効果があった工夫をシェアする
• 定期的に短い面談をお願いする
• 「協力してほしいこと」を一つに絞ってお願いする
先生には「一緒に考えてください」のスタンスが良いと思います。



その為には担任の先生に情報共有をしましょう。
相談すべきサイン


以下が見られる場合は、迷わず専門家につなぎましょう。
• 人との関わりで、周囲に迷惑をかけてしまう状況が多々ある
• どうしても家族以外の誰かがいると生活ができない
• 家庭だけでの対応が限界になっている



どうしても無理な状況になるのであれば、すぐに相談しましょう。耐えようとして親の精神が壊れてしまうと取り返しがつきません
まとめ
発達障害は「診断名」よりも「特性とのつきあい方」が大事です。
子どもの行動をみて自分達のせいだと思い悩む日々がありましたが、正しい情報を知り、支援を頼りに家庭でも工夫を積み重ね、親子ともに納得できる形に持っていきましょう。



最後までお読みいただきありがとうございました。
なかなか上手くいかないことも多いですが、少しずつ前に進んでいきましょう。