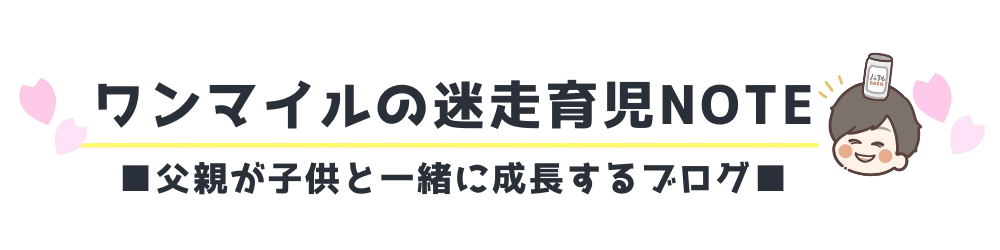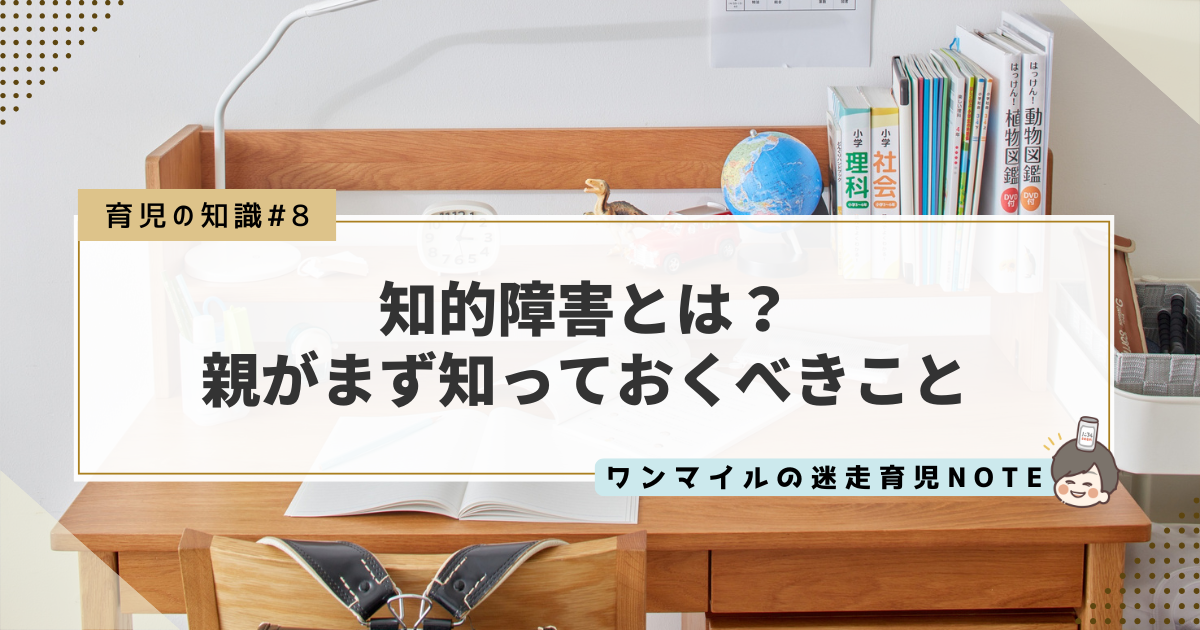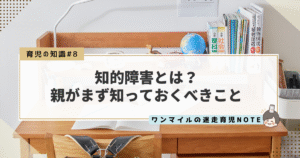はじめに
「知的障害」という言葉を耳にすると、正直なところ少し身構えてしまう方も多いのではないでしょうか。
「発達障害とはどう違うの?」「うちの子もそうなのかな?」――そんな不安を抱えながらも、なかなか人には相談できず、一人で悩んでしまう親御さんは少なくありません。
この記事では、知的障害の基礎知識から、診断の流れ、利用できる支援、そして家庭での関わり方までをまとめました。専門的な内容をわかりやすく噛み砕いていますので、「まず知っておきたい」親御さんに読んでいただける内容になっています。
 ワンマイル
ワンマイルまずは知っておくべきことを確認しておきましょう。
知的障害とは?


知的障害とは、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じている為、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義されています。
ここでいう「知的な働き」とは、単に勉強ができる・できないという話ではありません。物事を理解する力、問題を解決する力、相手の気持ちを推測する力なども含まれます。そして「適応力」とは、食事や着替え、買い物や交通機関の利用といった、日常生活を送るための力を意味します。
つまり、知的障害は「点数としてのIQ」だけで判断されるものではなく、生活全体でどのくらい支援が必要かが大切なポイントになります。
知的障害の分類と特徴
知的障害は重症度によって大きく4つに分けられます。
• 軽度(IQ50〜69)
学習には時間がかかりますが、読み書きや簡単な計算、身の回りのこともできることが多く、社会生活や仕事が可能な場合もあります。
• 中度(IQ35〜49)
簡単な日常会話や作業はできるようになりますが、発達がある程度の水準でとどまる。生活サポートが必要になってきます。
• 重度(IQ20〜34)
言葉の理解は限定的で、日常生活の基本的な動作にも継続した支援が必要です。
• 最重度(IQ20未満)
コミュニケーションを取ることが難しく、生活のほぼ全面的な介助が必要となります。
ただし、これはあくまで一つの目安です。成長速度や程度に関しては個人差があります。
知的障害と発達障害の違い
混同されやすいのが「発達障害」との違いです。
• 発達障害は、注意力やコミュニケーション、感覚の特性など「特定の分野」に凹凸がある場合が多いです。
• 知的障害は、知的な働き全般が平均より低く、日常生活全体に影響が出る点が特徴です。
ただし、両方を併せ持つケースもあります。たとえば「自閉スペクトラム症(ASD)+知的障害」という診断も珍しくありません。「どちらか」ではなく「重なり合う」こともあるということです。
診断・相談の流れ
「もしかしたら知的障害かもしれない」と感じるきっかけはさまざまです。
• 言葉の発達が遅い
• 集団行動が苦手
• 着替えやトイレの習得に時間がかかる
このようなサインが気になったら、まずは自治体の発達相談センターやかかりつけ小児科に相談してみましょう。
主に【知能検査】と【適応能力検査】の2つの検査によって総合的に診断が下されます。
知能障害診断に用いられる主な検査
知能検査(IQ測定)
知能の全体水準(IQ)と、言語・非言語の強み弱みを明らかにします。
■主な種類
●ウェイクスラー児童用知能検査
▷WISC-IV / WISC-V(ウェクスラー児童用知能検査)
• 対象:5歳~16歳
• 得られる結果:全検査IQ(FSIQ)/4つの指標(言語理解、知覚推理/視空間、ワーキングメモリー、処理速度)
▷WAIS-IV(ウェクスラー成人用知能検査)
• 対象:16歳~90歳
• 得られる結果:全検査IQ(FSIQ)/4つの指標(言語理解、知覚推理/視空間、ワーキングメモリー、処理速度)
※WPPSI(幼児用)として2歳〜7歳を対象とした検査もあります。
● 田中ビネー知能検査V
• 対象:2歳~成人
• 得られる結果:IQ(精神年齢÷生活年齢×100)と5領域(言語・記憶・推理・数量・知覚)
● KABC-II(カウフマン児童用知能検査)
• 対象:2歳半~18歳
• 認知処理過程に焦点(同時処理、継次処理など)
■検査結果として得られるもの
• 全検査IQ(知的能力の全体水準)
• 下位検査プロフィール(得意・不得意領域の把握)
• 発達年齢(精神年齢)
適応行動検査(生活力・社会性評価)
知能指数だけでなく、実際の生活での適応力を評価します。
本人・保護者・指導者への質問紙や面接で実施されます。
■主な種類
▷ Vineland-II 適応行動尺度(ヴィネランド)
• 対象:0歳~92歳
🔻評価領域🔻
• コミュニケーション(言語・理解・表出)
• 日常生活スキル(食事、身辺処理、家庭生活)
• 社会性(対人関係、遊び、社会的責任)
• 運動スキル(小児向け)
• 標準得点と適応行動年齢が算出される
▷ S-M 社会生活能力検査
• 対象:乳幼児~成人
• 評価領域:身辺自立、移動、作業、意志交換、集団参加、自己統制
• 発達年齢を算出
• ABS-S(適応行動尺度)
• 対象:乳幼児~成人
• 日常生活の自立・社会性を評価
■検査結果として得られるもの
• 適応行動標準得点/発達年齢
• 領域別プロフィール(例:生活は年齢相応だが、社会性が弱い)
• 実生活での支援の必要度
総合評価の流れ
- 知能検査(IQ70未満など)
- 適応行動検査(年齢に比して著しい遅れがあるか)
- 両方の結果+臨床所見を統合して、
DSM-5やICD-10/11の診断基準に照らして知的障害かどうかを判断。
支援・サポート体制


知的障害がある子どもは、年齢に応じてさまざまな支援を受けられます。
• 未就学期:療育センターや発達支援事業所での療育(ことば・運動・社会性のトレーニング)
• 学齢期:特別支援学級や特別支援学校、通級指導教室などでサポートを受けながら学習
• 成人期:就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)などで働く場や日中活動のサポート
また、家族向けには相談支援専門員や親の会などのつながりがあります。「同じ悩みを持つ親同士で話す場」は、想像以上に心強いものです。
まとめ
どうしても気になる行動があれば、まず一度診断に行き現状を確認してはいかがでしょうか。
手厚い支援先も多く、同じ悩みを抱える他の親御さんとも話す機会もあり、自分に合った支援先を見つけることがとても重要になります。



自分の心が壊れるくらいなら、この際とことん支援先を頼ってみるのも一つだと思います。最後までお読みくださりありがとうございました。